沖縄県内を歩いていると「石敢當(いしがんとう)」の文字をよく見掛けます。沖縄好きの皆さんには「何をいまさら」という方も多いかも!?と思いますが、今回は「石敢當」をはじめ、沖縄の「魔除け」や「おまもり」についてご紹介します。
辻々で見掛ける「石敢當」
沖縄の道を散策しているとT字路の突き当たりの壁や壁前でよく見かけるこの「石敢當」は、魔除けの意味で置かれています。沖縄の人たちは昔から悪霊を“マジムン”と呼び、その存在を恐れていましたが、“マジムンは直進しかできない”ということが信じられていましたので、T字路の突き当たりに「石敢當」を置いて、マジムンを撃退していたんですね。

この「石敢當」の起源は中国。もともとは“災いを取り除いて福を招く”目的だったものが、“魔物を駆除する”目的に変わっていったそうです。また、「石敢當」は中国古代の武人の名前と信じられていますが、これは俗説で起源も不明。石に対する信仰から生まれてきたとされています。

「石敢當」は沖縄県外でもみられますが、沖縄県内に多く見られるため、今では小型化して机の上に置けるような「石敢當」のかわいいミニチュアがお土産品として人気を博していますね。
「シーサー」は表情にも注目!
沖縄の魔除けとしては「シーサー」も馴染み深いと思います。この獅子像は沖縄ではさまざまなところに置かれていますが、民家の屋根の上に乗っているものを見かけたこともあると思います。
この屋根の上のシーサーは、それぞれの家の火の神様、沖縄の言葉で「ひぬかん」を守っているものです。火を使う台所に宿るとされる「ひぬかん」を屋根の上で守っているのがシーサーで、台所の真上の屋根の部分に置かれています。

ほかにも、開口、閉口の対になっているシーサーをよく見掛けると思いますが、城門や寺社の門によく見られて、一般的には口を開けている方が「オス」、口を閉ざしている方が「メス」とされています。

さらに、沖縄県内の現存する中で最も古いといわれているシーサーってご存知ですか? そう、八重瀬町(やえせちょう)の富盛にありますね。沖縄戦を経ても残り、戦時中の銃弾の跡が残っていて、当時の様子を今も伝えています。

「貝」を置く魔除け
門の上の「魔除け」としては、「シャコ貝」や「スイジ貝」「クモ貝」が有名です。「シャコ貝」は呪力(じゅりょく)があるとされていて、沖縄本島の東部、特に、うるま市の伊計島(いけいじま)や津堅島(つけんじま)によく見られます。

「スイジ貝」は形が「水」の字に似ているため、スイジ貝と呼ばれるようになったそう。また、「クモ貝」も6本の突起があるのが特徴で、共に門の上や石垣の上に置かれています。

かわいいおまもり「マース袋」
また、「おまもり」としては、お土産品にもなっている「マース袋」をご存知の人も多いのではないでしょうか。
「マース」は沖縄の言葉で「塩」という意味。マースは調味料としてだけでなく、清めの塩やおまもりとして、人々の生活の中に深く関わっていたのです。沖縄は島国なので、「旅」は常に危険と隣り合わせ。身を守ってくれるものとしてマースに祈りを込めて、身に付けていたそうです。

今では危険から身を守るだけでなく、開運や縁結びなどのめでたいものとして、財布やカバンに付けたり、受験の時の合格祈願として贈られたり、まさに縁起物。こちらもお土産品でかわいいカラフルなものが多く売られていますので、チェックしてみてください。
「サン」の力に守られる
さらに、おまもりをもう一つ。「サン/サングヮー」と呼ばれるものです。これは、弁当や法事で使われる重箱の上に置いてマジムンが食べ物を腐らせてしまうことから守ったり、子供たちを襲うマジムンの魔除けや厄除け用にかばんに付けたり、子供の夜泣きがすごい時に枕の下に入れたりすることもあるようです。
これらは小さいものですが、春に行われるシーミー(清明祭)や夏の旧盆の時期はすすきを使った大きいサングヮーを、玄関や家の敷地、井戸に置いて、また、農具や庭木などに結んで魔除けをします。

この「サン/サングヮー」もお土産品としてレザーやススキで作られたものが売っています。こちらもかわいいし、アクセサリーにもなりますね。
まもなく2020年が終わり、新年を迎えます。新しい年のおまもりとして、常に沖縄を感じられるアイテムとして、身に付けてみてはいかがでしょうか?
参考文献:沖縄大百科事典(沖縄タイムス社)、ビティしまツケンジマ(うるま市企画課)
さあ、オリオンビールで乾杯しましょう。
オリオンビール公式通販では、沖縄県外では手に入りにくいオリオンビール商品や沖縄県産品も取り扱っています。おうちでの「沖縄じかん」にぜひご活用ください。



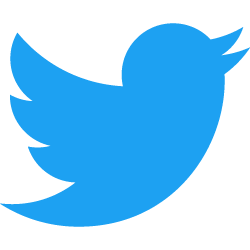
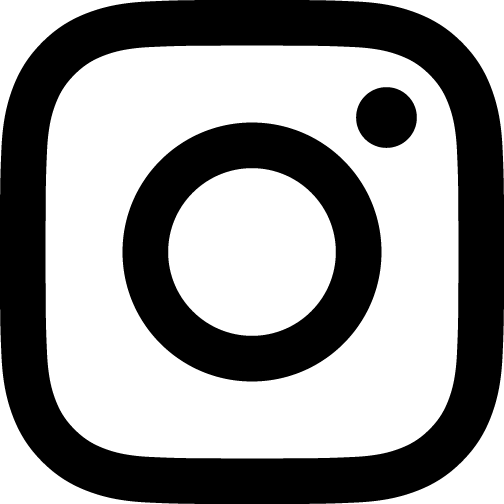
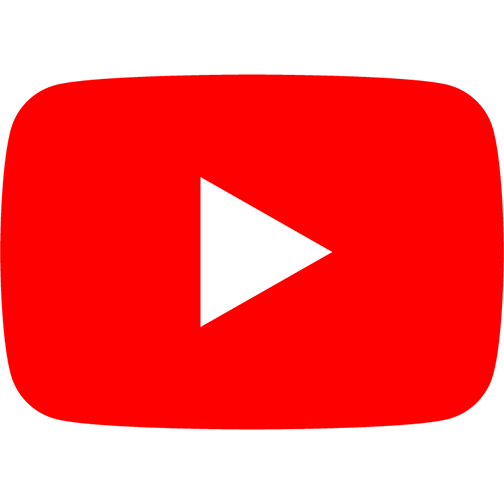










 75BEERリニューアル!あなたはどっちの新75BEER?選んで当てよう!こだわりグルメ♪75BEERがリニューアルして新島場!75BEER対象商品を1本以上購入したレシートを一口として応募しよう!TESIOのこだわりハムセットまたは沖縄県産冷凍車えびが当たる!
75BEERリニューアル!あなたはどっちの新75BEER?選んで当てよう!こだわりグルメ♪75BEERがリニューアルして新島場!75BEER対象商品を1本以上購入したレシートを一口として応募しよう!TESIOのこだわりハムセットまたは沖縄県産冷凍車えびが当たる!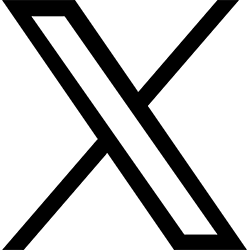




 飲酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。
妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。お酒は、おいしく、適量に。のんだあとはリサイクル
飲酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。
妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。お酒は、おいしく、適量に。のんだあとはリサイクル
